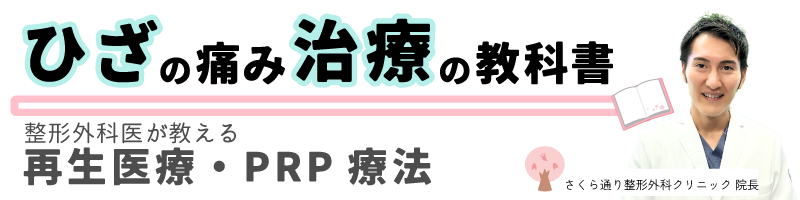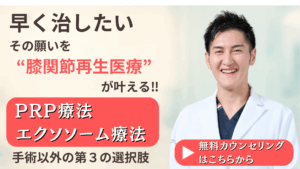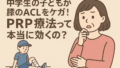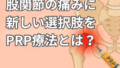1. 足首の捻挫は「ただのケガ」ではない
子どもが部活や体育の授業で「足をひねった」と帰ってきたとき、多くの保護者は「しばらく安静にしていれば治るだろう」と考えるかもしれません。
確かに、軽いねんざであれば数日で痛みが引き、普通に歩けるようになります。
しかし、中等度から重度のねんざでは、靭帯(骨と骨をつなぐ組織)が傷ついたり部分的に切れてしまったりすることがあります。

これを放置したり、十分に治療せずに無理して運動を続けたりすると、以下のようなリスクがあります。
-
繰り返しねんざを起こす「クセ」がつく
-
足首が不安定になり、転びやすくなる
-
将来の関節トラブルを抱えやすくなる
-
大人になってから変形性関節症につながる可能性
つまり、「たかがねんざ」ではなく、将来の健康にも関わる大事なケガなのです。
2. 従来の治療とその課題
これまでの一般的な治療は、RICE(安静・冷却・圧迫・挙上)で腫れを抑え、その後にリハビリで筋力やバランスを回復させる方法です。
ただし、
-
完全に回復するまで時間がかかる(数週間〜数か月)
-
子どもは安静を守れず、早く動いて再発しやすい
-
保護者が「どこまで運動させてよいか」判断に迷う
といった課題があります。特に運動部に所属する子どもは「試合に出たい」「休みたくない」と言いがちで、適切な治療と休養のバランスをとるのが難しい場面が多いのです。
3. 新しい選択肢「PRP療法」
そんな中、整形外科で最近、注目されているのがPRP療法です。

PRP(多血小板血漿)は、自分の血液を少し採って遠心分離機で分け、血小板が多く含まれる部分だけを取り出したものです。
血小板には「ケガを治すスイッチ」ともいえる成長因子が含まれており、組織の修復を促進します。
このPRPをケガした靭帯や関節に注射することで、自然に治る力を後押しするのがPRP療法です。
4. 子どもにPRP療法を検討するメリット
① 早い段階で痛みが減る
研究によると、PRPを受けた患者は5〜8週間で痛みや機能が改善しやすいと報告されています。
子どもは痛みに敏感で動きにくくなりがちですが、早期に痛みが和らげばストレスが少なくすみます。
② 部活や学校生活に早く戻れる
「大事な大会が控えている」「体育の授業を休みたくない」
子どもにとって運動できない期間は大きなストレスです。
PRPは競技復帰の期間を短縮できる可能性があるため、子どもの気持ちを尊重しながら安全に回復をサポートできます。
③ 手術を避けられる可能性がある
重度のねんざでは手術が必要になる場合もありますが、PRPは靭帯の修復を助けるため、保存療法で治せる範囲を広げる可能性があります。
④ 安全性が高い
PRPは自分の血液を使うため、アレルギーや拒絶反応のリスクがほとんどありません。
親として「副作用が心配」という不安が少ないのも大きなメリットです。
5. 実際の治療の流れ(保護者視点)
子どもにPRP療法を受けさせる場合、次のようなステップを踏みます。

-
診察:医師が足首の状態をチェックし、必要ならMRIやエコーで靭帯の損傷具合を確認。
-
採血:子どもの血液を少量採取。
-
PRP作成:採血した血を外部機関にPRPの作成を依頼します。作成するまでに約3週間程度かかります。
-
固定とリハビリ:最初は数週間程度の固定を行います。捻挫を初めてした場合と2回目の捻挫をした場合で固定期間は大きく異なり、捻挫を初めてした場合は一般的に4週間の固定を行うところが多いです。まその後、理学療法士の指導でリハビリを進める。
-
注射:エコーを使って、損傷部位に正確にPRPを注射。
保護者としては「注射は痛くないのか」「どれくらいで動けるのか」が気になるところですが、多くの場合、注射時の痛みは一瞬で済みます。どれくらいで動けるかについては損傷の程度にもより、固定期間は異なりますが、通常の治療よりも早く日常生活に復帰することが可能です。
6. 費用と注意点
費用
PRP療法は日本では保険適用外のことが多く、1回数万円〜10万円程度かかります。クリニックによって差がありますが、複数回行う場合はさらに費用がかかるため、事前に確認が必要です。
ちなみに、当クリニック(さくら通り整形外科クリニック)では再生医療(PRP療法・エクソソーム療法)を行っています。無料のカウンセリングも実施しておりますので、ご興味のある方はぜひ、一度、受診してお話しだけでも聞いてみてください。
再生医療の無料カウンセリングをご希望の方は、以下のバナーからお申し込みできます。
あなたにとって最適な選択を、一緒に考えていきましょう。
注意点
-
効果には個人差がある
-
短期的には効果的でも、半年後には通常治療との差が少なくなる場合がある
-
重度の靭帯断裂では手術が必要になることもある
7. 保護者ができるサポート
① 無理をさせない
子どもは「大丈夫!」と言って動こうとしますが、早すぎる復帰は再発のもとです。
医師や理学療法士の指示を守らせることが大切です。
② リハビリを続けさせる
PRPを受けても、筋力やバランス感覚を回復させるリハビリは欠かせません。
保護者がリハビリの大切さを理解し、家でもサポートしてあげましょう。
③ メンタルケア
運動できない期間は子どもにとって精神的に大きな負担になります。
焦りや不安を感じている子どもには「今は治すことが一番大事」と安心させてあげることも保護者の役割です。
8. 今後の研究と期待
現時点では「ねんざにPRPが効果的か」という研究は増えていますが、結果はまだ完全には一致していません。
短期的な痛みの軽減や機能改善には効果が期待できる一方で、長期的な再発予防や関節の健康維持にどの程度有効なのかは、これからの研究で明らかにされるでしょう。

まとめ(保護者向け)
足首のねんざは、子どもにとってよくあるケガですが、放置すると再発や将来の関節トラブルにつながることもあります。
PRP療法は、自己血を利用して治りを早める新しい方法であり、特に「早く部活に復帰したい」という子どもにとって有力な選択肢のひとつです。
保護者としては、
-
医師とよく相談して適応を見極める
-
費用や治療回数を確認する
-
子どもの焦りを抑えてリハビリを続けさせる
ことが大切です。
「子どもの未来の健康」と「今の活動への早期復帰」の両方を支える治療として、PRP療法を知っておくことは保護者にとって大きな意味があるでしょう。
参考文
- Humankinetics Journal of Sport Rehabilitation: Evidence of PRP injection reducing pain and improving function in lateral ankle sprains. Available at: https://journals.humankinetics.com/abstract/journals/jsr/33/7/article-p558.xml
- Journal of Medicine, University of Santo Tomas (JMUST): PRP therapy and its effect on return-to-play and pain reduction. Available at: https://www.jmust.org/elib/journal/doi/10.35460/2546-1621.2020-0077/pdf
- Randomized Clinical Study (2020): Treatment of lateral ankle sprain with PRP vs. immobilization only. Motus Sports Physical Therapy. Available at: https://motusspt.com/wp-content/uploads/2023/02/Treatment-of-lateral-ankle-sprain-with-platelet-rich-plasma-A-randomized-clinical-study-2020.pdf
- Frontiers in Bioengineering and Biotechnology (2022): Analysis of PRP in musculoskeletal injuries. Available at: https://www.frontiersin.org/journals/bioengineering-and-biotechnology/articles/10.3389/fbioe.2022.1073063/full
- Journal of Orthopaedic Surgery and Research (2024): Systematic review and meta-analysis of PRP in ankle pathologies. Available at: https://josr-online.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13018-024-05420-5
- Journal of Clinical Medicine (2023): Clinical application of PRP in foot and ankle pathologies. Available at: https://www.mdpi.com/2077-0383/12/3/1002
- Springer Review Article: Standard therapy of ankle sprains and rehabilitation perspectives. Available at: https://link.springer.com/article/10.1007/s43465-025-01418-1